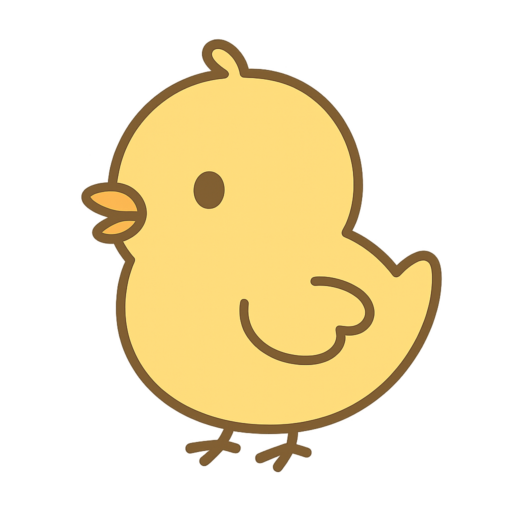「見て!下の歯が生えてきた!」 小さな白い歯がちょこんと顔を出した瞬間、本当に嬉しいですよね! 赤ちゃんの成長を感じる、感動的な出来事です。おめでとうございます!
そして、下の歯に続いて上の歯、横の歯…と、少しずつ歯が増えてくると、「ちゃんと食べ物噛めてるかな?」「あれ? 上下の歯の位置、ちょっとズレてる…?」「これって、将来の歯並びに影響しないかな?」なんて、今度は「噛み合わせ」のことが気になり始めるパパさん、ママさんも多いのではないでしょうか。
特に初めての育児だと、専門的なことはよく分からないし、心配になってしまいますよね。「歯並びや噛み合わせは、見た目だけでなく、健康にも大切」なんて聞くと、なおさらです。
そのお気持ち、とてもよく分かります。 今回は、そんな赤ちゃんの歯の「噛み合わせ」について、いつ頃から気にすればいいのか、お家でできること、そして心配な時の対処法などを、分かりやすく解説していきます!
いつ生える? 乳歯の生え方、基本のキ
まず、赤ちゃんの可愛い歯(乳歯)が、いつ頃、どんな順番で生えてくるのか、基本的なことを知っておきましょう。
生え始めの時期
早い子だと生後3ヶ月くらいから、多くは生後6ヶ月~9ヶ月頃に、下の前歯(真ん中の2本)から生え始めるのが一般的です。
でも、これはあくまで目安。1歳近くになってようやく生え始める子もいますし、生まれた時から生えている子(先天歯)も稀にいます。時期には大きな個人差があるので、周りの子と比べて遅くても、過度に心配しすぎないでくださいね。
生えそろう時期
2歳半~3歳頃までに、上下合わせて20本の乳歯がすべて生えそろうのが一般的です。
生える順番(一般的な目安)
- 下の前歯(乳中切歯)×2本
- 上の前歯(乳中切歯)×2本
- 上の横の歯(乳側切歯)×2本
- 下の横の歯(乳側切歯)×2本
- 奥歯(第一乳臼歯)×4本(上下左右1本ずつ)
- 尖った歯(乳犬歯)×4本(上下左右1本ずつ)
- 一番奥の歯(第二乳臼歯)×4本(上下左右1本ずつ)
この順番もあくまで目安で、多少前後することはよくあります。
赤ちゃんの噛み合わせ、心配するのはいつから?
「うちの子、ちょっと受け口に見えるかも…」「前歯が噛み合ってない気がする…」
歯が生え始めると、そんな風に見えることもあるかもしれません。でも、焦らないでください!
【~2歳半頃】乳歯が生えそろうまでは、様子見でOK!
この時期の赤ちゃんの噛み合わせは、まだ完成形ではありません。 歯が次々と生えてきている途中ですし、顎の骨もぐんぐん成長している真っ最中。そのため、一時的に上下の歯がズレて見えたり、歯と歯の間に隙間(空隙歯列)があったりするのは、ごく普通のことなんです。
歯が生えるスペースを確保したり、永久歯への生え変わりをスムーズにするために、ある程度の隙間やズレはむしろ必要な場合もあります。顎の成長とともに、噛み合わせも変化していきます。
この時期は、あまり神経質にならず、「今はまだ成長途中なんだな」と、おおらかな気持ちで見守ってあげましょう。
【3歳頃~】乳歯が生えそろったら、一度チェックを!
上下20本の乳歯がすべて生えそろうと、噛み合わせもある程度安定してきます。この時期(3歳頃)になっても、
- 受け口(反対咬合): 下の歯が上の歯より前に出ている
- 開咬(かいこう): 奥歯で噛んでも、前歯が噛み合わず開いている
- 交叉咬合(こうさこうごう): 上下の歯が横にズレて噛み合っている
などの状態が明らかに気になる場合は、一度、歯科医に相談することを検討しても良い時期です。
乳歯の噛み合わせの問題が、将来の永久歯の歯並びや、顎の骨の成長に影響を与えてしまう可能性があるためです。
【健診を活用!】1歳半&3歳児健診
これらの時期に行われる乳幼児健診には、歯科健診が含まれていることが多いです。虫歯だけでなく、歯並びや噛み合わせについても、専門家の目でチェックしてもらえる良い機会なので、必ず受けるようにしましょう。
将来のために! 赤ちゃんの良い噛み合わせを育む生活習慣
噛み合わせには、生まれつきの骨格など遺伝的な要因も関係しますが、日々の生活習慣が影響を与えることもあります。お家で少し意識できることをご紹介します。
「カミカミ」しよう! よく噛んで食べる習慣を
離乳食の進め方
月齢に合わせて、ドロドロから少しずつ形のあるものへステップアップ。「カミカミ、モグモグ」を促しましょう。丸呑みの癖をつけないように。
食材の工夫
成長に合わせて、少し歯ごたえのある野菜スティックなどを取り入れるのも◎。(ただし、喉に詰まらせないよう、側で見守り、食材の大きさや硬さには十分注意してください!)
食事環境
テレビなどを消して、食事に集中できる、落ち着いた環境で、ゆっくり食べる時間を大切に。
「噛む」という行為は、顎の骨や周りの筋肉をしっかり発達させます。これが、歯がきれいに並ぶための土台作りになるのです。唾液もたくさん出るので、虫歯予防にもつながります。
気になる「癖」はありませんか? 指しゃぶりなどへの対応
指しゃぶり
赤ちゃんの指しゃぶりは、精神安定のための自然な行為なので、1~2歳の頃は無理にやめさせる必要はありません。しかし、3~4歳を過ぎても長く続いていたり、頻度が高かったりする場合は、指の圧力で上の前歯が出っ張ったり、上下の前歯が噛み合わなくなったり(開咬)する原因になることがあります。
その他の癖
唇を噛む癖、舌で前歯を押す癖なども、同様に歯並びに影響を与える可能性があります。
無理やりやめさせようとすると、かえって執着してしまうことも。まずは、なぜその癖が出るのか(不安、寂しさ、手持ち無沙汰など)理由を探ってみましょう。他の楽しい遊びに誘ったり、安心できるようにスキンシップを増やしたりするのも良い方法です。長く続く場合は、歯科医や保健師さんに相談してみましょう。
寝る姿勢や頬杖にも、ちょっと注意?
いつも同じ方向を向いて寝るうつぶせ寝や、頬杖をつく癖が習慣になっていると、顎に継続的な力がかかり、歯並びや顔の形に影響が出る可能性も指摘されています。絶対にダメというわけではありませんが、気にかけてあげると良いでしょう。
お口ポカンはサインかも? 鼻呼吸を意識しよう
いつも口をポカンと開けている「口呼吸」が癖になっていると、舌が正しい位置(上顎についている状態)に収まらず、口周りの筋肉のバランスが崩れて、歯並び(特に出っ歯や開咬)や顔つきに影響が出ることがあります。
鼻詰まりが原因の場合は、耳鼻科で診てもらいましょう。癖になっている場合は、意識して口を閉じるよう促すこともありますが、なかなか難しい場合も。気になる場合は、歯科医や耳鼻科医に相談してみましょう。
正しい鼻呼吸は、舌や口周りの筋肉を適切に発達させ、正常な顎の成長を促します。
乳歯の虫歯、あなどらないで!
「どうせ生え変わるから」と乳歯の虫歯を放置してしまうと、大変なことに! 虫歯が進行して乳歯を早くに抜くことになると、隣の歯が倒れてきたりして、永久歯が本来生えるべきスペースがなくなってしまい、歯並びが悪くなる大きな原因になります。
毎日の仕上げ磨きを丁寧に行い、フッ素塗布や定期的な歯科検診で、虫歯をしっかり予防しましょう!
あれ?やっぱりおかしいかも… 噛み合わせが気になった時の相談先
「色々気をつけてはいるけど、やっぱりうちの子の噛み合わせ、気になる…」
「健診で指摘されちゃった…」
そんな時は、一人で悩まず、専門家に相談しましょう!
相談先は?
- かかりつけの小児歯科医: まずは、子どもの歯の専門家である小児歯科医に診てもらうのが一番です。赤ちゃんの口の中全体の状態を見て、的確なアドバイスをくれます。
- 地域の保健センター(保健師・歯科衛生士): 乳幼児健診だけでなく、個別の育児相談や歯科相談に応じてくれます。気軽に相談できる窓口です。
- 矯正歯科専門医: 小児歯科医からの紹介や、より専門的な判断が必要な場合に相談します。
相談するタイミングの目安は?
- 3歳児健診などで指摘された場合。
- 乳歯が生えそろっても、明らかに受け口、開咬、交叉咬合などが改善しない、または悪化しているように見える場合。
- 噛み合わせが原因で、うまく食べられない、発音しにくいなどの問題が出ている場合。
すぐに治療が始まるの?
乳歯の噛み合わせの問題に対して、すぐに本格的な矯正治療が始まることは稀です。多くの場合、まずは経過観察となります。
- 必要に応じて、指しゃぶりなどの癖を改善するための指導やトレーニングを行ったり、マウスピースのような簡単な装置を使ったりすることもあります。
- ワイヤーなどを使った本格的な矯正治療は、一般的に永久歯が生え始めてから(小学生以降)検討されることが多いです。
大切なのは、早めに専門家の意見を聞き、適切なタイミングで必要な対応をとれるようにしておくこと。 そして、専門家の話を聞くことで、親御さん自身の不安が解消されることも大きなメリットです。
焦らず見守ろう! 赤ちゃんの健やかな歯と口を育むために
赤ちゃんの噛み合わせは、乳歯が生えそろうまでは、まだまだ成長途中の不安定なものです。すぐに「おかしい!」と決めつけず、まずは日々の成長を温かく見守ってあげてくださいね。
そして、
- よく噛んで食べる習慣をつける
- 気になる癖に気を配る
- 虫歯をしっかり予防する
といった、お家でできることを続けながら、定期的な歯科健診を忘れずに受けることが、赤ちゃんの健やかな歯と口を育むための基本です。
もし、どうしても気になることや心配なことがあれば、一人で悩まず、抱え込まず、気軽に専門家(小児歯科医や保健師さんなど)に相談してください。 きっと、あなたの不安に寄り添い、的確なアドバイスをくれるはずです。
健康な歯と良い噛み合わせは、赤ちゃんがしっかり栄養を摂り、はっきりおしゃべりし、そして自信を持って笑顔でいられるための大切な土台です。焦らず、愛情を持って、お子さんの口の健康をサポートしていきましょう!