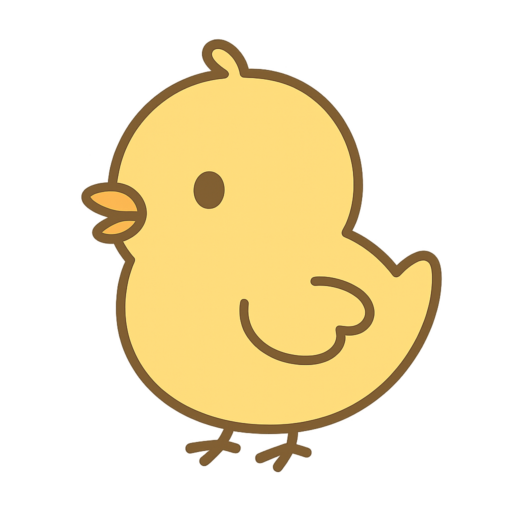授乳の後、抱っこしてゲップをさせていたら…「げぷっ」と、飲んだばかりのミルクや母乳を赤ちゃんが吐き戻しちゃった! 「あーあ、またお着替えか…」なんて思いながらも、「ちゃんと飲めてるのかな?」「もしかして、どこか具合が悪いのかな?」と、心配な気持ちでいっぱいになるママさん、パパさん、本当にお疲れ様です。
特に初めての育児だと、吐き戻しの量や回数に一喜一憂してしまいますよね。「うちの子、よく吐くけど大丈夫?」その不安、とってもよく分かります。
赤ちゃんの吐き戻しは、見ているこちらも辛いし、お洗濯も増えて大変…。でも、その多くは赤ちゃんならではの理由があるんです。
今回は、そんな赤ちゃんの吐き戻しについて、どうして起こりやすいのか、心配な吐き戻しとそうでないものの見分け方、そしてお家でできる対応策などを分かりやすく解説します!正しい知識で、少しでも不安を解消しましょう。
どうして赤ちゃんはよく吐くの? その体の仕組みとは
大人はそんなに頻繁に吐いたりしないのに、どうして赤ちゃんはあんなによく吐き戻してしまうのでしょうか? それには、赤ちゃんならではの体の仕組みが関係しています。
胃の形が「とっくり型」
大人の胃は、食べ物が入り口から入り、カーブして下に溜まる「J字型」をしています。でも、赤ちゃんの胃は、まだ縦に長く、とっくりのような形をしています。そのため、飲んだミルクや母乳が溜まりにくく、ちょっとした刺激やゲップと一緒に逆流しやすいのです。
胃の入り口の筋肉(噴門)がゆるゆる
胃の入り口には、食べ物が食道へ逆流しないようにキュッと締める筋肉(噴門括約筋)があります。でも、赤ちゃんはこの筋肉の働きがまだ未熟でゆるいため、飲んだものが食道の方へ戻りやすいのです。
消化機能がまだ未発達
一度にたくさんの量を消化する力も、まだ大人ほど強くありません。
空気を一緒に飲み込みやすい
母乳を飲む時や哺乳瓶でミルクを飲む時、赤ちゃんは一生懸命。その際に、ミルクや母乳と一緒に空気をたくさん飲み込んでしまうことがあります。その空気がゲップとして出る時に、一緒に中身も出てきてしまうのです。
飲みすぎちゃった!
赤ちゃんの胃は小さいので、気持ちよく飲んでいるうちに、胃の容量以上に飲んでしまうことも。そんな時は、余分な分を吐き出すことがあります。
これらの理由から、赤ちゃんにとって吐き戻しは、ある程度「生理的な現象」であり、決して珍しいことではない、ということをまず知っておきましょう。
これって大丈夫? 見分けたい「心配ない吐き戻し」と「受診すべき吐き戻し」
「生理的なものなら安心!」…と言いたいところですが、中には注意が必要な吐き戻しもあります。ここでしっかり見分け方を知っておきましょう!
これは心配ないかも? 生理的な吐き戻し(溢乳:いつにゅう)の特徴
機嫌が良い◎
吐いた後もケロッとしていて、普段と変わらず元気で、ニコニコしている。
体重が順調に増えている◎
吐き戻しはするけれど、しっかりと栄養は摂れていて、母子手帳の成長曲線に沿って体重が増加している。
吐く量が比較的少ない◎
ダラダラと口からこぼれる程度、またはゲップと一緒に少量「げぷっ」と出るくらい。(※ただし、洋服に広がると少量でも多く見えることがあります)
吐いたものの色がミルクや母乳の色◎
白っぽい、または少し黄色みがかったミルクの色、あるいは少し消化されてヨーグルト状になっている。
これは要注意! すぐに病院へ! 受診の目安となる心配な吐き戻し
以下のサインが見られたら、自己判断せずに、速やかに小児科を受診しましょう。夜間や休日でも、症状によっては救急相談(#8000など)や救急外来の受診を検討してください。
噴水のように勢いよく吐く! (噴出性嘔吐)
毎回、または頻繁に、飲んだものを大量に、まるで噴水のようにビシャーッ!と勢いよく吐く。
もしかしたら、肥厚性幽門狭窄症(胃の出口が狭くなる病気)など、外科的な処置が必要な病気の可能性も考えられます。
吐いたものに血が混じっている! (赤黒い、コーヒーかす様など)
明らかに血液と分かるものや、古くなった血のような黒っぽいものが混じっている。
ママの乳首が切れていて、そこから出た血を赤ちゃんが飲んで吐き戻すこともあります。まずはママの乳首の状態も確認してみてください。
吐いたものが緑色や黄色! (胆汁色)
明らかにミルクや母乳の色ではない、緑色や濃い黄色(胆汁の色)のものを吐いた場合。
腸閉塞など、緊急性の高い病気のサインである可能性があります。
吐いた後、ぐったりしている、顔色が悪い、機嫌が極端に悪い!
いつもの元気がない、あやしても笑わない、顔色が悪く青白いなど、全身状態が悪い。
発熱、下痢、お腹の張りなど、他の症状も一緒に出ている!
胃腸炎などの感染症にかかっている可能性があります。
体重が増えない、または減っている!
吐き戻しが原因で、必要な栄養が十分に摂れていない可能性があります。
脱水症状かも?
おしっこの回数や量が極端に少ない(半日以上出ていないなど)、口の中や唇がカサカサに乾いている、皮膚の張りがなくシワシワしている、目が落ちくぼんでいる、泣いても涙が出ないなど。
少しでも楽に! 吐き戻しを減らすための7つの工夫
心配ない吐き戻しだと分かっても、やっぱり頻繁だとママもパパも大変ですよね。少しでも吐き戻しを減らすために、お家でできる工夫を試してみましょう。
【基本のキ!】授乳後のゲップはしっかりと!
赤ちゃんを縦抱きにして、背中を下から上へ優しくさすり上げたり、軽くトントンしたりして、ゲップを出させてあげましょう。授乳の途中(特に哺乳瓶の場合、半分くらい飲んだところなど)で一度ゲップを挟むのも効果的です。
胃の中に入った空気を先に出すことで、ミルクや母乳が空気と一緒に出てくるのを防ぎます。
【食後は安静に】授乳直後は激しく動かさない!
授乳後すぐに、おむつ替えで足を高く持ち上げたり、うつ伏せ遊びをさせたり、チャイルドシートに座らせて揺らしたりするのは避けましょう。しばらくは縦抱きにするか、バスタオルなどで上半身を少し高くして、安静にさせてあげると良いでしょう。
【飲みすぎ注意?】一度に飲ませる量を調整(哺乳瓶の場合)
赤ちゃんが欲しがるままにあげるのではなく、月齢に応じた適切な量を心がけましょう。もし一度にたくさん飲んで吐き戻すようなら、1回の量を少し減らして、授乳回数を増やすなどの工夫も。
【道具を見直す】哺乳瓶の乳首のサイズは合ってる?
乳首の穴が大きすぎると、ミルクが勢いよく出てしまい、赤ちゃんがむせたり、空気をたくさん飲み込んだりする原因になります。月齢に合った乳首を選びましょう。ゲップが出にくい子向けの特殊な形状の哺乳瓶を試してみるのも一つの手です。
【飲む姿勢も大切】授乳時の姿勢を工夫
母乳の場合
ママが少し上体を起こした(リクライニングのような)姿勢で授乳すると、赤ちゃんの頭が少し高くなり、飲み込みやすくなります。
哺乳瓶の場合
哺乳瓶の角度を調整し、乳首の先端まで常にミルクで満たされている状態を保つようにしましょう。
【寝かせ方も一工夫】寝かせる時の体勢
授乳後しばらくは、赤ちゃんの頭が少し高くなるように、バスタオルなどを背中の下に敷いて緩やかな傾斜をつけて寝かせてあげるのも良いでしょう。(ただし、窒息の危険がないよう、顔の周りには何も置かず、常に赤ちゃんの様子を確認できる状態にしてください!)
ゲップが出にくい場合は、体の右側を下にして寝かせると、胃の形状からゲップが出やすいと言われることもあります。しかし、SIDS(乳幼児突然死症候群)の予防の観点からは、基本的には「仰向け寝」が推奨されていますので、右向きにする場合は短時間にし、目を離さないようにしましょう。
吐き戻しは成長の過程。心配しすぎず、でもサインは見逃さずに!
赤ちゃんの吐き戻し。多くの場合は、体の機能がまだ未熟なために起こる、成長過程の一つの姿です。月齢が進み、消化機能が発達し、おすわりやハイハイで体が起きてくるようになると、自然と回数は減っていきます。
大切なのは、「心配ない吐き戻し」と「注意すべき吐き戻し」のサインをしっかり見極めること。
お家でできる工夫を試しながら、あまり神経質になりすぎず、赤ちゃんの機嫌や体重増加など、全体的な様子をゆったりと見てあげてくださいね。
そして、どうしても心配な時や、「これはちょっとおかしいかも?」と感じるサインが見られた時は、決して一人で悩まず、迷わず小児科医に相談しましょう。 何もなければ安心できますし、もし何か病気が隠れていたとしても、早く気づいて対応することができます。
今は、吐き戻しのお世話で大変な毎日かもしれませんが、必ず落ち着く時期はやってきます。それまで、どうか肩の力を少し抜いて、できる範囲で、赤ちゃんと向き合っていってくださいね。応援しています!