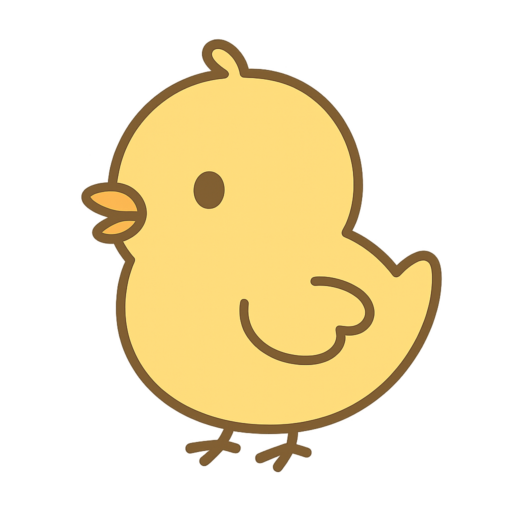深夜、ようやく寝たと思った赤ちゃんが、また大きな声で泣き出した…。 抱っこしても、ゆらゆらしても、おっぱいをあげても、何をしても泣き止まず、一向に寝てくれない…。
そんな眠れない夜が続くと、体はクタクタ、心もヘトヘトになりますよね。 「いつまでこれが続くんだろう…」 「どうしてうちの子だけ泣き止まないの?」 「私の抱っこの仕方が悪いのかな…?」 そんな風に、暗い部屋で一人、途方に暮れたり、自分を責めてしまったりすることもあるかもしれません。
本当によく頑張っていますね。毎日、毎晩、本当にお疲れ様です。 夜泣きは、経験した人にしか分からない、本当に過酷な試練だと思います。
でも、あなたは決して一人ではありません。 多くのママやパパが、同じように悩み、試行錯誤しながら、この大変な時期を乗り越えています。
今回は、そんな眠れない夜を過ごすあなたの心が少しでも軽くなるように、夜泣きの基本的な知識から、抱っこしても寝てくれない時の具体的な対処法をぎゅっと詰め込んでお伝えします。
赤ちゃんの夜泣き、なぜ起こるの? その原因と時期
そもそも「夜泣き」とは、お腹が空いた、おむつが気持ち悪い、暑い・寒い、具合が悪いといったはっきりした理由がないのに、赤ちゃんが夜中に目を覚まして泣き出し、なかなか寝付かないことを指します。
なぜ夜泣きが起こるのか、その明確な原因は実はまだよく分かっていません。ですが、一般的には以下のような要因が考えられています。
睡眠リズムがまだ未熟だから
生まれたばかりの赤ちゃんは、昼も夜も関係なく、短いサイクルで寝たり起きたりを繰り返します。成長とともに徐々に体内時計が整い、夜にまとまって眠れるようになりますが、その発達過程で、夜中に目が覚めてしまいやすいのです。
脳が発達している証拠!
赤ちゃんの脳は、日々たくさんの情報を吸収し、猛スピードで発達しています。その過程で、日中に受けた刺激を睡眠中に整理しきれず、脳が興奮状態になって目を覚ましてしまう、とも言われています。また、赤ちゃんは大人よりも浅い眠り(レム睡眠)の割合が多いことも関係しているようです。
生活リズムの影響
日中の過ごし方(活動量や昼寝の時間など)や、寝る前の習慣が、夜の睡眠に影響することもあります。
不安やストレスを感じている?
ママやパパのイライラや不安が赤ちゃんに伝わってしまったり、環境の変化(引っ越し、保育園入園など)があったりすると、夜泣きにつながることも。
その他
歯が生え始める時の不快感(歯ぐずり)や、一時的な体調の変化(鼻詰まり、便秘など)が隠れている場合もあります。
夜泣きが始まる時期や続く期間は、本当に個人差が大きいものです。一般的には、生後3ヶ月頃から始まり、生後6ヶ月~1歳半頃にピークを迎えることが多いと言われていますが、全く夜泣きをしない子もいれば、2歳を過ぎても続く子もいます。
終わりは必ず来る! 夜泣きと上手に付き合うための心構え
先が見えない夜泣きは本当につらいですが、向き合い方の心構えを少し変えるだけで、気持ちが楽になるかもしれません。
自分を責めない!
夜泣きは、赤ちゃんのせいでも、あなたのせいでもありません。「私の育て方が悪いから…」なんて、絶対に思わないでくださいね。
完璧を目指さない
「絶対に泣き止ませなきゃ」「すぐに寝かせつけなきゃ」と気負いすぎると、余計にプレッシャーを感じてしまいます。泣き止まない時があっても大丈夫。
「いつか終わる」と信じる
夜泣きは、赤ちゃんの成長過程における一時的なもの。「このトンネルも、いつか必ず抜けられる!」と信じて、長い目で捉えましょう。
情報に振り回されない
ネットや本には様々な夜泣き対策がありますが、効果は赤ちゃんによって様々。「〇〇が良いらしい」と試してダメでも落ち込まず、「うちの子には合わなかったんだな」と、他の方法を探してみましょう。
チームで乗り切る!
夜泣き対応は、ママ一人の仕事ではありません! パパと夜間の対応を交代したり、日中の家事や育児を分担したり、おじいちゃんおばあちゃんに頼ったり…家族というチームで協力し合うことが不可欠です。
あなたの休息が最優先!
これが一番重要かもしれません。赤ちゃんが寝ている時は、家事など後回しにして一緒に寝る! 日中でも、意識的に休息時間を確保する! あなたの心と体の健康を守ることが、結果的に赤ちゃんへの穏やかな対応につながります。
抱っこしてもダメ…泣き止まない夜に試したい! 夜泣き対処法10連発
「抱っこしても全然泣き止まない…もう打つ手がない…」そんな時に、試してみてほしい対処法を10個ご紹介します。必ず効くとは限りませんが、引き出しの一つとして持っておくと、少し心強いかもしれません。
1.【基本の確認】まずは原因を探る!
意外な原因が隠れていることも。お腹は空いてない? おむつは気持ち悪くない? 部屋は暑すぎたり寒すぎたりしない? 鼻は詰まってない? 服のタグなどがチクチクしてない? まずは基本的な不快の原因がないかチェックしましょう。
2.【抱っこの工夫】体勢を変えてみる
いつもの横抱きでダメなら、縦抱き、コアラ抱っこ(ママと向かい合わせ)、飛行機抱っこ(うつ伏せ気味に腕に乗せる)など、抱き方を変えてみましょう。 ママやパパの体にしっかり密着させて、心音を聞かせるのも安心効果があると言われています。おくるみで包んであげるのも◎(特に低月齢の場合)。
3.【音の魔法】ホワイトノイズを聞かせる
テレビの「ザー」という砂嵐の音、換気扇や空気清浄機の「ゴー」という音、ドライヤーの音、ビニール袋をクシャクシャする音、波の音…。こうした単調な音(ホワイトノイズ)は、赤ちゃんがお腹の中で聞いていた音に似ているため、安心させる効果があると言われています。専用のアプリや、音が出るぬいぐるみなどを活用するのも手です。
4.【声の力】優しく歌う・話しかける
ママやパパの優しい声は、赤ちゃんにとって最高の安定剤。静かな子守唄を歌ってあげたり、「大丈夫だよ」「よしよし、眠ろうね」と穏やかなトーンでゆっくり話しかけてあげたりしましょう。
5.【環境チェンジ①】部屋の環境を変える
いつも真っ暗なら、少しだけ間接照明をつけてみる。逆に、豆電球が点いているなら消してみる。部屋の温度や湿度を快適な状態に調整してみる。ほんの少し環境を変えるだけで、落ち着くこともあります。
6.【環境チェンジ②】場所を変えて気分転換
泣き止まない時は、思い切って寝室からリビングへ移動してみましょう。窓を開けて、少しだけ外の空気に触れさせてあげるのも効果的な場合があります。(深夜なので、安全と防寒には十分配慮してくださいね!)環境が変わることで、赤ちゃんの気分がリセットされることがあります。
7.【触れ合いの癒し】マッサージ&スキンシップ
優しく背中をトントンしたり、円を描くようにお腹をマッサージしたり。肌と肌が触れ合うことで、安心ホルモン「オキシトシン」が分泌され、親子ともにリラックス効果が期待できます。
8.【お守り代わりに】授乳してみる
お腹が空いていなくても、おっぱいやミルクを吸う行為(吸啜行動)そのものに、赤ちゃんを落ち着かせる効果があります。ただし、これを頻繁にやりすぎると、「夜中に起きる=おっぱい・ミルク」という癖がついてしまう可能性もあるので、バランスを見ながら試してみましょう。
9.【日中の対策】生活リズムを見直す
即効性はありませんが、長い目で見ると一番効果的な対策かもしれません。
- 朝は毎日同じ時間に起こし、太陽の光を浴びせる。
- 日中は、お散歩や外気浴、室内遊びなどで適度に体を動かす。
- 月齢に合ったお昼寝時間を心がけ、寝かせすぎない。
- 寝る前は、テレビやスマホなどの強い光を避け、お風呂→授乳→絵本→子守唄のように、**毎日決まった入眠儀式(ねんねルーティン)**を行う。
体内時計を整え、「夜は眠る時間」というリズムを体に覚えさせていくことが、夜泣きの根本的な改善につながります。
10.【最終手段?】ドライブにGO!
車の規則的な振動とエンジン音が心地よくて、すんなり寝てしまう赤ちゃんもいます。ただし、深夜の運転は危険も伴います。パパと協力したり、無理のない範囲で安全運転を心がけて。赤ちゃんを乗せるときは必ずベビーシートを利用し、どうしても泣き止まないときの最終手段として考えましょう。
暗いトンネルの先には光が! 夜泣き、みんなで乗り越えよう
赤ちゃんの夜泣きは、本当につらく、孤独を感じやすいものですよね。でも、どうか忘れないでください。夜泣きは一時的なものであり、必ず終わりが来ます。
「これをすれば絶対泣き止む!」という魔法のような特効薬はありません。試行錯誤の毎日だと思います。うまくいかない日があっても、決して自分を責めないでくださいね。
色々な対処法やグッズを試しながら、「これなら少し楽かも」「この方法だと寝てくれることが多いな」という、あなたと赤ちゃんに合ったやり方を、焦らず見つけていければ大丈夫です。
そして、絶対に一人で抱え込まないでください。 パートナーと、家族と、そして地域のサポートと、手を取り合って、この大変な時期を乗り越えていきましょう。
今、この瞬間も、眠い目をこすりながら、必死で赤ちゃんをあやしているあなたへ。 本当によく頑張っています。その頑張りは、必ず赤ちゃんに届いています。
暗くて長いトンネルのように感じるかもしれませんが、必ず光は見えてきます。応援しています!