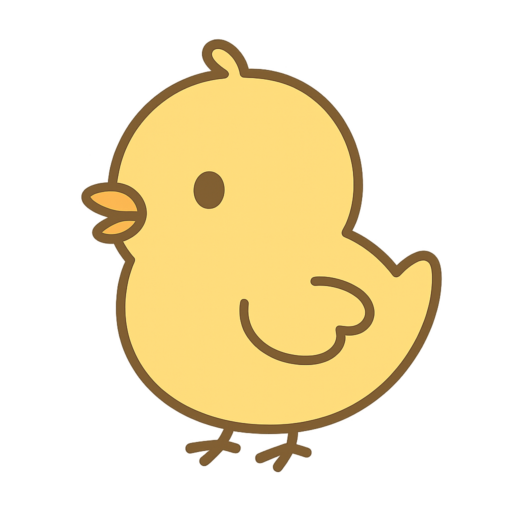生後6ヶ月を迎えた赤ちゃんのママさん、パパさん、本当にお疲れさまです!
半年という節目まで、赤ちゃんを愛情たっぷりに育ててきたことは本当に素晴らしいことです。
赤ちゃんの成長を日々感じながら、頑張ったご自身をたくさん褒めてあげてくださいね。
生後6ヶ月の赤ちゃんは、5ヶ月の頃と比べて、さらに活動的で好奇心旺盛になります。
おすわりが徐々に安定し始めたり、寝返りやずりばいで移動範囲が広がります。
また、下の前歯が生え始める赤ちゃんもいて、歯が生えることによる不快感でぐずりがちになることもあります。
生後6ヶ月の赤ちゃんの1日
6ヶ月の赤ちゃんは夜間にまとまった睡眠をとることが増え、1日の合計睡眠時間は13~14時間程度です。昼寝も1~2回程度、各1~2時間ほど行います。
離乳食を開始して1ヶ月が経ったころから、1日2回に増やすタイミングでもあり、食事時間が徐々に生活リズムの一部として定着してきます。
いつもの授乳のうちさらにもう1回離乳食を増やし、毎日同じ時間に2度の離乳食をあげるようにします。
離乳食の進め方(6ヶ月)
離乳食を開始して1ヶ月経つと、多くの赤ちゃんは1日2回の離乳食に進めるタイミングになります。
新しい食材は1つずつ試し、アレルギー反応を注意深く観察しましょう。
食材は柔らかく、なめらかなペースト状から徐々に舌でつぶせる固さへ進めます。
赤ちゃんが食べることに抵抗がある場合は無理せず、様子を見ながら進めましょう。
離乳食が終わったら、赤ちゃんが欲しがるだけ母乳を与えます。この時期はまだほとんどの栄養を母乳やミルクで賄っているので、離乳食の栄養バランスや量は気にする必要はありません。
5ヶ月のころ同様、アレルギー反応があったときに備えて、新しい食材を試す場合はかかりつけ医が開いている時間を選びましょう。
6ヶ月は一番体調を崩しやすい時期
赤ちゃんは、生まれたときにママから免疫を受け継いでいます。
その免疫が、新生児の免疫力が未熟な時期を守ってくれるのですが、生後6ヶ月を過ぎると、母体から受け継いだ免疫が徐々に切れていきます。
そのため、6ヶ月ごろから赤ちゃんは感染症にかかりやすくなり、発熱や体調不良を起こすことが多くなります。
外出後の手洗いや消毒、赤ちゃんが使うおもちゃや食器類の衛生管理を徹底するとともに、赤ちゃんの体調に注意を払うようにしましょう。
とはいえ、一度も熱を出さない赤ちゃんはほとんどいません。
6ヶ月を過ぎたら赤ちゃんは熱を出したり風邪を引いたり下痢をしたりするものだと心構えをして、予め対処法を確認したり、自宅で様子を見るのか病院を受診するべきかの判断基準などを調べて、いざというときに備えておきましょう。
夜泣きが始まる赤ちゃんも
6ヶ月頃から夜泣きが始まる赤ちゃんもいます。
夜泣きは個人差が大きく、まったくしない赤ちゃんもいれば、1歳ごろから始まる赤ちゃんもいるなど、本当に人それぞれです。
基本的な対策としては、
- 日中にお散歩したりたくさん体を動かして体力を使わせてあげる
- 夕方以降はあまり興奮させるような遊びをやめる
- 就寝する1時間前までにお風呂を済ませる
などを心がけると、夜間にぐっすり眠れる傾向がありますが、それでも夜泣きをする赤ちゃんもたくさんいます。
夜中にぐずって起きてしまった場合、どの対処法が効果的かは赤ちゃんによります。
抱っこで落ち着く子もいれば、授乳や背中を優しくトントンすることで落ち着く子もいます。外に散歩にいったり、子守唄を歌ってあげると落ち着く子もいます。
何を試してもなかなか効果がない場合もありますが、パートナーや家族と協力し、焦らず無理せず乗り切りましょう。
夜中に延々泣かれるとママやパパの精神的な負担も大きいですが、夜泣きは必ず終わります。一人で抱え込まず、周囲のサポートを活用しましょう。
6~7ヶ月健診について
自治体によっては6~7ヶ月健診が実施されます。
健診では、赤ちゃんの体重・身長の測定、おすわりや寝返りの状況、視覚や聴覚の確認、離乳食の進み具合などをチェックします。
赤ちゃんの発達状態ついては、普段の生活の中で赤ちゃんの反応に何か気になる点はないかなどを聞かれたりもしますので、事前に普段の様子を思い返して、気がかりな点があればメモをしておくといいでしょう。
また、この時期は予防接種のタイミングと重なることも多いので、可能であれば健診のタイミングで同時に予防接種も済ませると、手間が省けるかもしれません。
そろそろ歯が生えはじめます
6ヶ月ごろになると、赤ちゃんによっては歯が生え始めます。
赤ちゃんの歯は一般的に下の前歯2本から生え、その後、上の前歯、側切歯、奥歯と順に生えそろいます。
ですが、歯の生える順番や時期は赤ちゃんによって個人差が大きく、時期も順番も前後することがよくあります。
他の歯が生えたのにいつまでたっても前歯だけが生えない、というような場合ならともかく、順番が前後しても歯が生えてきているならあまり気にする必要はありません。
どうしても不安な場合は、かかりつけ医や小児対応している歯科などに相談しましょう。
前歯が生え始めたばかりの時期は、歯の形も凹凸がなく滑らかな形をしていて赤ちゃんの唾液の分泌も多いので、まだ本格的な歯磨きは必要ありません。
唾液で十分に汚れが落とせるので、今の段階では口内を清潔に保つことよりは、今後の歯磨きをスムーズに始めるため、口周りや口内に指やガーゼで優しく触れて、口周りや口内を触られることに慣れさせておくといいでしょう。
生後6ヶ月の赤ちゃんの発達
生後6ヶ月になると、興味あるものを積極的に掴んで遊び、物を落とすと音がすることに気づき楽しみます。
寝返りが自在になり、腹ばいからお座りへの移行を試みたり、ずりばいを始める赤ちゃんもいます。
人見知りに加えて、ずりばいができるようになると後追いが始まることがあります。
気づかないうちに赤ちゃんが足もとに来ていたり、ママやパパの後を追って思わぬ場所まで移動してしまったりするので、ベビーサークルやゲートなどを活用して、赤ちゃんが動き回っても安全な空間を用意してあげましょう。
喃語がますます複雑になり、赤ちゃんによっては言葉に意味があることを理解し始め、「あーあ」「うーう」のような簡単な発音でものを指し示すようになることがあります。
生後6ヶ月の赤ちゃんの接し方
活動範囲が広がるため、転倒や誤飲に注意し、環境を安全に整えましょう。
赤ちゃんが自分で移動できるようになると、一気に怪我や事故のリスクが高まります。赤ちゃんの視点で家の中を総点検し、危険なものを隔離するとともに、転倒して家具や柱の角などに頭を打ち付けたりしないように、コーナーガードを設置するのもよいでしょう。
体調を崩しやすくなる時期なので、感染症対策のため衛生管理を徹底しましょう。
また、夜泣きをする赤ちゃんの場合は対応に個人差があるため、いろいろな方法を試し、パートナーや家族の協力を得るようにしましょう。
まとめ
生後6ヶ月は成長の個人差が出やすい時期です。
周囲と比較して焦らず、赤ちゃんそれぞれのペースを大切にし、穏やかな気持ちで成長を見守っていきましょう。
自分自身の休息も意識しながら、赤ちゃんとの毎日をゆったりと楽しんでくださいね。