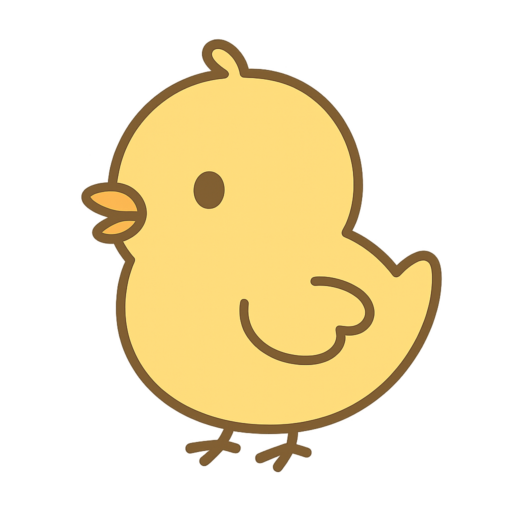赤ちゃんがスプーンを差し出すと、いつも右手で受け取る。おもちゃを掴むのも、なぜか左手が多い気がする…。 そんな日々のちょっとした仕草を見て、「あれ? もしかして、この子の利き腕って決まってきたのかな?」「どっち利きになるんだろう?」なんて、ふと気になる瞬間はありませんか?
特に初めての育児だと、「利き腕っていつ頃はっきりするの?」「もし左利きだったら、何か特別なことをしてあげた方がいいのかな?」など、色々な疑問や、ほんの少しの心配が湧いてくるかもしれませんね。
我が子の成長の一つひとつに気づき、その子の個性や発達に興味を持つのは、親としてとても自然なことです。今回は、そんな赤ちゃんの「利き腕」に関する気になる疑問について、分かりやすく解説していきます!
赤ちゃんの利き腕、判明するのはいつ? 気になる時期を解説
まず、結論から言うと、赤ちゃんの利き腕(利き手)がはっきりと定まる時期には、大きな個人差があります。焦って判断する必要はありませんが、一般的な目安としては、次のような流れで進んでいくことが多いようです。
【探り探りの乳児期(0歳~1歳頃)】まだ決まっていない時期
この時期の赤ちゃんは、右手を使ったり、左手を使ったり、両手を一緒に使ったりと、どちらの手も同じように使うことがほとんどです。おもちゃを持つ手が毎回違ったり、左右交互に使ったりするのも、ごく自然な姿です。
この時期は、脳の発達(特に、体の左右の動きをコントロールする脳の役割分化)も、体の使い方も、まだ成長途中。赤ちゃんは、色々な動きを通して、「どっちの手が使いやすいかな?」と、まさに探り探りの状態なのです。
もし、生後6ヶ月~1歳を過ぎても、極端に片方の手しか使おうとしない(例:常にもう片方の手は握ったまま、など)様子が見られる場合は、使わない方の手に何か動かしにくい原因(麻痺など、ごく稀なケースですが)がないか、念のためかかりつけの小児科医に相談してみても良いかもしれません。(ただし、多くの場合心配いりません!)
【なんとなく見えてくる幼児期(2歳~4歳頃)】傾向が見え始める時期
2歳を過ぎる頃から、少しずつ特定の側の手を好んで使う傾向が見られ始めます。お絵かきをする時、スプーンを持つ時、ボールを投げる時など、「こっちの手の方が使いやすそうだな」という場面が増えてきます。
脳の左右の得意分野がはっきりしてきたり、日々の経験を通して、よりスムーズに動かせる手が定着してきたりするためと考えられています。
【ほぼ確定!の幼児期後半(4歳~6歳頃)】定着する時期
多くの子どもで、4歳~6歳頃には利き腕がほぼ定着すると言われています。小学校に上がる前には、ほとんどの場合で「この子は右利きだな」「左利きだな」というのが、周りの目から見てもはっきりしてきます。
脳機能の専門化が進み、文字を書くなど、より複雑で精密な手の動きが求められるようになるにつれて、得意な方の手が主として使われるようになるためです。
ポイントは、赤ちゃんの利き腕は、数ヶ月や1年といった短い期間で決まるものではなく、成長とともにゆっくりと定まっていく、ということです。
どっちの手をよく使う? 利き腕を見分けるヒント
「じゃあ、うちの子はどっちかな?」と気になる場合は、日常生活の中で、どんな時にどちらの手をよく使っているか、少し意識して観察してみると良いかもしれません。
- 食事の時: スプーン・フォークを持つ手は? コップを持つ手は? 手づかみ食べで、最初に出る手は?
- お絵かきの時: クレヨンやペンを持つ手は?
- 遊ぶ時: ボールを投げる手は? 積み木を高く積むとき、上に乗せる方の手は? おもちゃを操作する時によく使う手は?
- 生活の中で: 歯ブラシを持つ手は? ドアノブを回す手は?
【観察の注意点】
- 一つの動作だけで判断しない: 食事は右手だけど、お絵かきは左手、という子もいます。色々な場面で、どちらの手をより頻繁に、より器用に(上手に)使っているかを、総合的に見てみましょう。
- 決めつけない: 中には、動作によって使う手が違う「クロスドミナンス(交差利き)」(例:書くのは右手、投げるのは左手)や、どちらの手も同じくらい上手に使える「両利き」の人もいます。
- 無理に試さない: 「ほら、こっちの手で持ってごらん」などと、無理に利き腕を判断しようとしたり、テストのように試したりする必要はありません。自然な様子を観察しましょう。
世界的に見ても多数派! なぜ右利きの人が多いの?
世界的に見ると、人口の約9割が右利きだと言われています。なぜこれほど右利きが多いのでしょうか? その理由は、まだ完全には解明されていませんが、いくつかの説があります。
- 遺伝説: 右利きになりやすい遺伝子がある、という考え方。でも、左利きの両親から右利きの子が生まれることも多く、遺伝だけでは説明しきれません。
- 脳の機能説(有力説): 人間の脳は、左脳と右脳で得意な役割が分かれています。多くの場合、言葉を話したり、論理的に考えたりする左脳が優位に働きます。そして、左脳は体の右半身の動きをコントロールしているため、結果的に右利きが多くなる、という説です。
- 環境・文化説: ハサミや急須、駅の自動改札など、世の中の道具や設備は、右利きの人が使いやすいように作られているものが多数派です。こうした環境や、昔からの社会的な慣習が、右利きを優勢にしている、という考え方もあります。
おそらく、これらの要因が複雑に絡み合って、右利きが多数派になっているのだろうと考えられています。
右利き、左利き、どっちがいいの? 優劣なんてありません!
「うちの子、もしかして左利きかも…?」そう思った時、少し心配になる方もいるかもしれません。昔は、「左利きは不便だから」と右利きに直すべきだ、という風潮があった時代もありました。
でも、現代では利き腕に優劣はない、というのが一般的な考え方です。
利き腕は、その人の脳の特性によって自然に決まるものであり、知能や運動能力の優劣とは全く関係ありません。
無理に利き手を直そうとすることは、子どもにとって大きなストレスになります。混乱してしまったり、ぎこちない動きになったり、字を書くのが嫌いになったり、さらには自信をなくしてしまう可能性もあります。
「左利きの人は芸術的センスがある」「スポーツで有利」などと言われることもありますが、科学的な根拠がはっきりしない話も多く、安易に一般化するのは避けたいところです。
大切なのは、右利きであろうと左利きであろうと、それはその子の個性の一部であると認め、本人が自分の利き手に自信を持って、自然に使えるようにサポートしてあげることです。
もし我が子が左利きだったら? サポートのポイントと注意点
もし、お子さんが左利きかな?と感じたら、以下の点を少しだけ心に留めておくと、よりスムーズにサポートできるかもしれません。
大前提は、無理に矯正しないこと。本人が自然に使っている手を、そのまま受け入れてあげましょう。これが一番大切です。
生活環境にちょっとした配慮を
食事の席
右隣の人と肘がぶつからないように、食卓の左端に座らせてあげるなどの工夫を。
道具
左利き用のハサミや文房具、おたま、急須など、便利なグッズも販売されています。本人が困っているようなら、試してみるのも良いでしょう。(ただし、無理に全て揃える必要はありません。本人が工夫して使えるなら、それでOK!)
文字を書く時
- 基本的な鉛筆の持ち方や書き順は、右利きと同じです。
- ただ、左利きの子が書きやすいように、紙を少し右に傾けたり、手首の角度を少し変えてみたりすると書きやすくなる場合もあります。無理のない範囲でアドバイスを。
- お手本は、右側か、もしくは上の方に置いてあげると見やすいことが多いです。
- 大切なのは、書くこと自体が嫌いにならないように、優しくサポートすることです。
肯定的な声かけを!
「左利きってカッコいいね!」「野球のイチロー選手も左利きなんだよ」など、左利きであることをポジティブに捉えられるような言葉をかけてあげましょう。周りから「あれ?左利きなの?」と言われた時に、本人が気にしないように、親が「そうなんだよ、カッコいいでしょ!」と明るく返してあげるのも良いですね。自分の利き手に自信を持ち、自己肯定感を育む手助けになります。
園や学校の先生にも伝えておこう
入園・入学の際には、担任の先生に「この子は左利きです」と伝えておくと、席の配置や道具の使い方などで、必要な配慮をしてもらいやすくなります。
ポイントは、過剰に特別扱いする必要はないけれど、右利きが多数派の社会の中で、ほんの少し不便を感じる場面があるかもしれない、ということを理解し、必要に応じてさりげなくサポートしてあげる、という姿勢です。
右利きでも左利きでも大丈夫! 我が子の個性を大切に見守ろう
赤ちゃんの利き腕は、一朝一夕に決まるものではなく、数年かけてゆっくりと定着していくものです。
親としては、どちらの手が利き手になるのか、つい気になってしまうものですが、一番大切なのは、右利きであろうと左利きであろうと、それがその子の個性の一部であると受け止め、温かく見守ることです。
無理に利き手を直そうとしたり、「こっちの方が良い」という優劣をつけたりする必要は全くありません。お子さんが、自分の使いやすい手を、自信を持って、自然に使えるように、そっとサポートしてあげてください。
右の手も、左の手も、これからたくさんの物事に触れ、経験を掴み取り、未来を切り拓いていく、お子さんの大切な手です。その成長を、これからも愛情深く応援していきましょう!