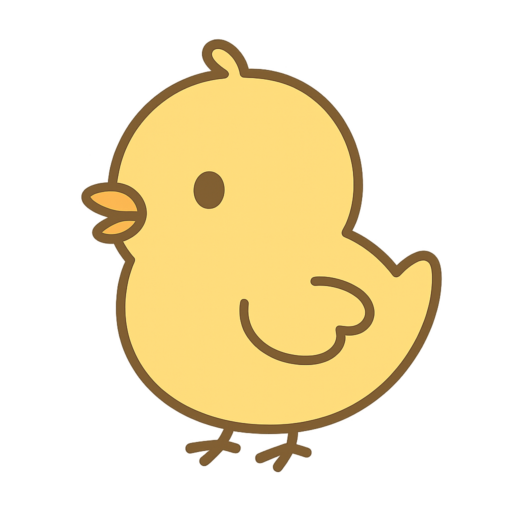よちよち歩きが始まったり、指差しで何かを教えてくれたり、「マンマ」「ブーブー」など意味のある言葉が出始めたり…この一年で、赤ちゃんは目覚ましい成長を遂げましたね。できることが増える喜びと同時に、周りの子との違いや発達のペースが気になり始める時期かもしれません。
特に、1歳半健診が近づいてくると、「うちの子、言葉がちょっと遅いかも…」「あんまり目が合わない気がする」「遊び方にこだわりが強いかな?」など、些細なことが気にかかり、「もしかして、自閉症スペクトラム障害(ASD)なのかな…?」と、ふと不安がよぎることもあるのではないでしょうか。
その心配な気持ち、本当によく分かります。我が子のことを一生懸命見ているからこそ、小さなサインにも気づくのですよね。
今回は、そんなママさん、パパさんの気持ちに寄り添いながら、1歳児に見られることがある自閉症スペクトラム障害(ASD)のサインや、その向き合い方について、知っておきたい情報をお伝えします。
大切なのは、一人で悩まず、正しい知識を得て、必要なら専門家のサポートを求めることです。
自閉症スペクトラム障害(ASD)ってどんな特性?
まず、基本的なことをおさらいしましょう。自閉症スペクトラム障害(ASD)は、生まれつきの脳機能の発達のかたよりが原因で起こる発達障害の一つです。親の育て方や環境のせいではありません。
主な特性として、以下の2つが挙げられます。
対人関係や社会的コミュニケーションの難しさ
- 目を合わせたり、人の表情を読み取ったりするのが苦手
- 他の子どもや周りの人への関心が薄く見える
- 言葉の発達がゆっくりだったり、独特な話し方をしたりすることがある
- 指さしや身振りなど、言葉以外でのコミュニケーションが苦手
特定のものやことへの強いこだわり、感覚の偏り
- 興味の対象が非常に限られている
- 同じ遊びを何度も繰り返したり、物の配置や手順に強いこだわりを見せたりする
- 音や光、触覚などの感覚が非常に過敏だったり、逆に鈍感だったりする
「スペクトラム」という名前の通り、これらの特性の現れ方や強さは、本当に人それぞれ。一人ひとり違う、虹のような多様性を持っています。
ASDは「病気」ではなく、その子の「特性」です。治療で「治す」のではなく、その子の特性を理解し、本人が安心して力を発揮できるよう、周りの環境を整えたり、コミュニケーションを工夫したりといった「支援(サポート)」をしていくことが大切になります。
【気づきのヒントとして】1歳児に見られるASDのサイン
1歳頃になると、0歳の頃よりも社会性やコミュニケーションに関わる行動が増えてくるため、ASDの特性に気づくきっかけも増えるかもしれません。
ただし、ここでも非常に重要な注意点があります。
これから挙げるサインは、あくまで「後にASDと診断されたお子さんによく見られたと言われる1歳代の特徴」であり、これらに当てはまるからといって、必ずしもASDであるとは限りません。 1歳代もまだまだ発達の途上であり、個人差が非常に大きい時期です。1歳半健診などで発達の遅れを指摘されても、その後の成長で追いついたり、特性が目立たなくなったりするケースもたくさんあります。
チェックリストのように捉えず、あくまで「我が子をより深く理解するためのヒント」として、お読みください。
目が合いにくい、人の顔をあまり見ない
抱っこや授乳中なども、視線が合いにくかったり、合ってもすぐに逸らしてしまったりする。人の表情への関心が薄いように見える。
名前を呼んでも振り向かないことが多い
聴力に問題がないのに、はっきり名前を呼んでも、なかなかこちらを見ない状態が続く。
指さしをしない(要求・共感・追視)
- 要求: 欲しいものがある時、指をさして「あれ取って」と伝えようとしない。(代わりに、大人の手を持って行こうとする「クレーン現象」が見られることも)
- 共感: 見つけたもの(犬、飛行機、好きなキャラクターなど)を指さして、「見て見て!」と親の注意を引こうとしない。
- 追視: 親が「あ、ワンワンだよ」と指さした方向を目で追おうとしない。
指さしは、他者と興味や注意を共有する「共同注意」の重要なサイン。1歳代でのこの行動の有無は、コミュニケーション発達の一つの目安とされます。
意味のある言葉がほとんど出ない
「ママ」「パパ」「ワンワン」「ブーブー」など、意味を理解して使っている言葉が1つか2つ程度、あるいは全く出てこない。
注意: 言葉の発達スピードは個人差が非常に大きいため、「言葉が遅い=ASD」ではありません。他のサインと併せて見ることが大切です。
簡単な身振りの模倣をしない
「バイバイ」「パチパチ」「ちょうだい(どうぞ)」などの簡単なジェスチャーを真似しようとしない。
大人の動きを真似ることは、社会性を学ぶ上で大切なステップです。
一人遊びが多く、周りの子に関心がないように見える
公園や支援センターなどで、他の子どもたちが遊んでいても、興味を示さず、一人で黙々と自分の好きな遊びをしていることが多い。
遊び方が独特・限定的
- おもちゃを本来の遊び方とは違う方法で、繰り返し遊び続ける(例:ミニカーを走らせず、タイヤだけをずっと回している)。
- 物をきれいに一列に並べることに強いこだわりがある。
- 同じ動き(体を揺らす、手をひらひらさせるなど)を繰り返す(常同行動)。
感覚の過敏さ・鈍麻さが目立つ
- 特定の音(掃除機、ドライヤー、子どもの歓声など)を異常に怖がる。
- 特定の素材の服や、食べ物の食感を極端に嫌がる。
- 逆に、頭をぶつけてもあまり痛がらなかったり、寒さ・暑さに鈍感に見えたりする。
- くるくる回るものや光るものを、飽きずにずっと見つめている。
繰り返しになりますが…
これらのサインは、あくまで「傾向」であり、いくつかのサインが当てはまったとしても、それだけでASDと判断することはできません。聴力や視力の問題、他の発達上の課題、あるいはその子の個性や気質である可能性も十分に考えられます。
心配しすぎないで。1歳での診断はまだ難しいことも
1歳半健診は、子どもの発達を確認する大切な機会です。この健診で、言葉の遅れやコミュニケーション面での心配などを指摘され、経過観察となったり、専門機関への相談を勧められたりすることもあるかもしれません。
指摘を受けると、やはり不安になってしまいますよね。でも、健診での指摘が、すぐにASDの確定診断につながるわけではありません。
- 1歳代は、まだ発達の変化が大きい時期であり、診断するには早すぎることが多い。
- その後の成長とともに、気になる行動が目立たなくなることもある。
- ASDの診断には、一定期間の行動観察や、複数の専門家による多角的な評価が必要。
もし健診で何か指摘されたとしても、「うちの子はASDなんだ」とすぐに決めつけてしまうのではなく、「我が子の発達をより丁寧に見守り、サポートしていくためのきっかけをもらった」と捉える視点も大切です。
不安な気持ちが強い場合は、診断を急ぐことよりも、まずは保健師さんや専門機関に相談し、「今、この子のためにできる関わり方」についてアドバイスをもらうことから始めてみてはいかがでしょうか。
心配なサインは成長のサインかも。焦らず、専門家と一緒に見守ろう
1歳という節目は、たくさんの成長が見られる嬉しい時期であると同時に、発達に関する心配事が出てきやすい時期でもあります。
今回ご紹介したASDのサインと言われるものは、あくまで早期の「気づき」のためのヒントであり、お子さんにレッテルを貼るためのものでは決してありません。
一人で悩まない
気になることがあれば、抱え込まずに、1歳半健診の機会を活用したり、地域の保健センター、かかりつけの小児科医、児童発達支援センターなどに気軽に相談してみましょう。専門家は、客観的な視点でアドバイスをくれ、必要であれば適切なサポートにつなげてくれます。早期に相談することで、親御さんの不安が和らぎ、前向きな一歩を踏み出すきっかけになります。
比べない、焦らない
子どもの成長ペースは一人ひとり違います。周りの子と比べるのではなく、昨日より今日、少しでもできたこと、成長したことを見つけて、たくさん褒めてあげてください。それがお子さんの自信につながります。
我が子の「今」を大切にする
たとえ気になるサインがあったとしても、それはその子の個性の一部かもしれません。良い面もたくさんあるはずです。診断名にとらわれすぎず、目の前にいる我が子の「今」としっかり向き合い、愛情を持って関わっていくことが何よりも大切です。
そして、毎日頑張っているパパさん、ママさん自身も、どうか無理をしすぎないでくださいね。時には息抜きをして、心と体を休める時間も大切にしてください。応援しています!