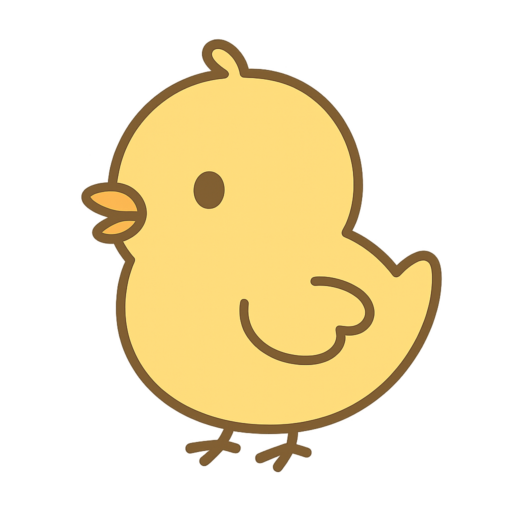生後9ヶ月を迎えた赤ちゃんのママさん、パパさん、本当にお疲れさまです!
9ヶ月という長い期間を、毎日の愛情深い育児と共に過ごされてきたことは素晴らしいことです。ここまでの努力をしっかりねぎらいながら、引き続き穏やかな気持ちで赤ちゃんとの日々を楽しんでくださいね。
生後9ヶ月になると赤ちゃんの行動はさらに活発で積極的になります。
ハイハイがスピードアップし、つかまり立ちや伝い歩きを始める赤ちゃんも増えてきます。
指先がより器用になり、小さなものを掴むことが上手になります。
また、表情や感情表現がさらに豊かになり、自分の意志をはっきり示すようになります。
朝の着替えを嫌がったり、両手をあげて抱っこを要求するようになったりと、赤ちゃんの自我が芽生え始めます。
生後9ヶ月の赤ちゃんの1日
この頃の赤ちゃんの睡眠は1日12〜14時間程度で、昼寝は午前と午後の2回が一般的です。
夜間の睡眠も長くなり安定します。離乳食はそろそろ後期に入り、1日3回に回数を増やすころです。
日中は遊びや探索活動がより活発になり、周囲の環境への関心も強まります。ママやパパに対する後追いも多くの赤ちゃんがするように。
社会的な能力も発達し、ママやパパの声を聞いたり表情を見たりすることで、喜んでいるとか怒っているといった感情を理解することができるようになります。
同時にママやパパを特別な存在として認識し、一人遊びをしていても、数分に一度振り向いてママやパパがそばにいることを確認したりします。
振り向いたら大好きなママやパパがちゃんといて、自分のことを見ていてくれて優しく笑ってくれる、ということを確認することで、赤ちゃんは安心して一人で遊ぶことができます。
赤ちゃんに自我が芽生え、自分の意志や欲求が出てくる時期ですので、赤ちゃんの気持ちに寄り添ってあげるようにしましょう。
家の中の安全確保を
生後9ヶ月の赤ちゃんは行動範囲がさらに広がりますので、家庭内の安全確認を行いましょう。
- 階段や段差にはゲートを設置する
- 家具の角にはクッションをつける
- 小さなものや危険物(電池や薬品など)は手の届かない場所に片付ける
- コンセントや配線にはカバーを設置する
赤ちゃんが自由に安全に探索できる環境を整えることで、安心して遊ばせることができます。
9ヶ月ころは、掴まり立ちができるようになる赤ちゃんや、つかまり歩きを始める赤ちゃんもいます。
掴まり立ちができるようになると、ローテーブルや本棚、戸棚の少し高さのある段まで赤ちゃんの手が届くようになります。
今までは赤ちゃんの手が届かないと思っていたエリアがどんどん危険になっていきますので、お家の中を総点検して安全を確保しましょう。
離乳食後期(1日3回)への進め方
9ヶ月頃になると、そろそろ離乳食を1日3回へと増やす時期になります。
赤ちゃんのようすを観察し、以下のような条件をクリアしているなら、離乳食を1日3回に増やしても良いころ合いです。
- 口をモグモグよく動かして食べることができる
- 手づかみ食べを始めるなど食べることに対して意欲がある
- ある程度のかたさのものを歯茎で潰して噛むことができる
- 安定して一人で座っていられる
離乳食を1日3回に増やす場合、離乳食と離乳食の間隔は4時間以上空け、3回目の夕食は19時までには済ませましょう。これは消化を促し、夜間の良質な睡眠を確保するためです。
離乳食が1日3回になると、一日の栄養の大半は離乳食で賄うようになります。栄養バランスの良い食材を選び、噛む練習になるよう少しずつ固さを調整しながら進めます。
一方、赤ちゃんによっては食べむらが出てきたり、好き嫌いが出来たりするころです。
昨日はスムーズに食べた食材なのに今日は一口も食べない、といったこともよくありますので、あまり気にせず、赤ちゃんの気分に合わせて翌日再チャレンジしたり、調理法を変えたりご飯に混ぜたり工夫をしながら進めましょう。
また、そろそろコップで水を飲む練習を始めてもいいころです。最初はママやパパがコップを支えてあげて、慣れてくれば赤ちゃんに自分でコップを持たせてあげて。
なるべく大人と同じ時間に食事を摂ることで、ママやパパが美味しく楽しくご飯を食べている姿を見せることも、大事な食育です。食事のリズムを整え、食事への興味を養ってあげましょう。
大人中心の生活だとついつい夕食の時間が遅くなりがちですが、3回目の離乳食が遅くなってしまうと赤ちゃんもどんどん就寝の時間が遅くなり、早起きが出来なくなってしまいます。
早寝早起きの生活リズムを維持するためにも、赤ちゃん中心の生活リズムを大人も一緒になって守っていきましょう。
9~10ヶ月健診をうけましょう
生後9ヶ月を越えると9〜10ヶ月健診があります。
9〜10ヶ月健診では、身体の発達状況(身長・体重測定、ハイハイやつかまり立ちの状態)や離乳食の進み具合を確認します。不安なことは医師や保健師に積極的に相談しましょう。
ただし、人見知りのピークの時期ですので、健診の場ではぐずってしまって何もできない…ということもよくあります。
そういう場合も、親御さんから赤ちゃんの普段の様子をヒアリングすることで健診を行うことが出来ますので、心配する必要はありません。
生後9ヶ月の赤ちゃんの発達
生後9ヶ月になると、物の用途や位置を理解し、簡単な指示を理解して反応を示します。
ハイハイがさらに上達し、つかまり立ちや伝い歩きを始める赤ちゃんもいます。
人見知りや後追いのピークですが、同時に身近な人への信頼と愛着が深まります。
「ママ」「パパ」といった意味のある単語を真似して言い始める子もいます。喃語もさらに発達し、コミュニケーションが活発になります。
生後9ヶ月の赤ちゃんの接し方
感情表現が豊かになり、自我が芽生え始める時期です。赤ちゃんが何を伝えようとしているのかをよく観察し、気持ちを尊重する接し方を心掛けましょう。
また、8ヶ月のころと比べてさらに活発になります。つかまり立ちを始める赤ちゃんも多く、赤ちゃんの手の届く範囲が上方向に大きく広がります。
今まで手が届かなかった棚の二段目三段目や、台やローテーブルの上などに置いてあるものにも赤ちゃんの手が伸びるようになるので、改めて赤ちゃんが触れると危険なものや、誤飲の可能性があるものがないかチェックしましょう。
感染症への抵抗力がまだ弱いので、手洗いやおもちゃの消毒などの衛生管理を継続しましょう。
まとめ
生後9ヶ月は赤ちゃんの活動範囲が広がり、日々成長が実感できる時期です。
赤ちゃんの好奇心と安全面を両立できる環境作りを意識しながら、焦らず赤ちゃんのペースに寄り添い、家族みんなで楽しく育児を続けていきましょう。
ご自身の健康や休息も忘れず、穏やかな気持ちで赤ちゃんとの素敵な時間を積み重ねていってくださいね。