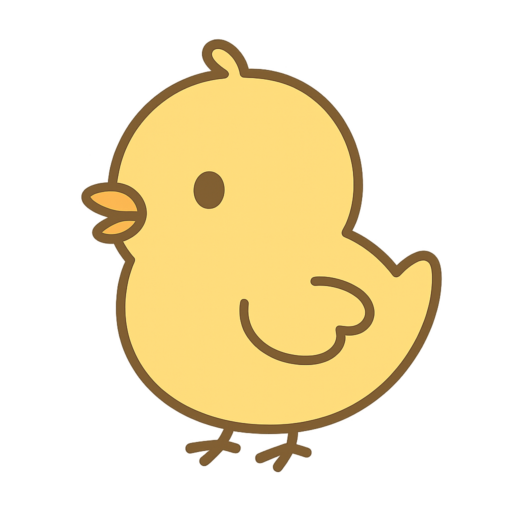1歳の赤ちゃんをお持ちのママさん、パパさん、いつも子育てお疲れ様です!
よちよち歩きが始まり、行動範囲がぐんと広がったり、「マンマ」「ブーブー」といった意味のある言葉が出始めたり、指差しで一生懸命何かを伝えようとしたり…。毎日、驚くようなスピードで成長していく我が子の姿に、感動と喜びでいっぱいの日々をお過ごしのことと思います。
そんな目覚ましい成長の中で、「あれ?うちの子、言葉を覚えるのがすごく早いかも」「パズルや積み木が、教えなくてもできちゃう!」「一度見たものを驚くほどよく覚えている…」など、周りの子と比べて「すごい!」と感じる瞬間はありませんか?
そんな時、ふと「もしかして、この子は特別な才能を持っているのかも?」「『ギフテッド』って聞いたことあるけど、うちの子もそうだったりして…?」なんて、我が子の秘めたる可能性に期待が膨らむこともあるかもしれませんね。
その気持ち、とてもよく分かります。我が子の持つ素晴らしい才能を見つけ出し、その可能性を最大限に引き出してあげたいと願うのは、親として当然のことですよね。
今回は、「ギフテッド」とは何か、そして1歳の頃に見られるかもしれない特徴や、才能の有無に関わらず大切にしたい向き合い方について、一緒に考えていきましょう。
ギフテッド=天才? 知っておきたい基本的なこと
まず、「ギフテッド(Gifted)」という言葉について確認しましょう。これは「(神様から)与えられたもの」という意味合いを持つ言葉です。一般的には、知的能力(IQが高いなど)、創造性、特定の学術分野、芸術、リーダーシップ、運動能力などの領域で、同年齢の子どもと比べて著しく高い能力や可能性を示す人を指す概念として使われています。
単に「頭が良い」ということだけでなく、
- 突き抜けた好奇心や探求心
- 高い集中力、没頭力
- 豊かな感受性や共感性
- 独創的な発想力
なども、ギフテッドの特徴として挙げられることがあります。
ただし、「ギフテッド」の明確な定義は世界共通ではなく、国や専門家によって捉え方が異なります。また、優れた才能を持つ一方で、発達にアンバランスさ(凸凹)があり、そのために周りの環境に馴染めず「生きづらさ」を感じるケースがあることも、大切なポイントです。
1歳児に見られるギフテッドの特徴
1歳になると、歩行が始まり、言葉が出始め、指差しでのコミュニケーションも活発になるなど、できることが格段に増えます。そのため、もしギフテッドの特性があれば、0歳の頃よりも具体的な行動として現れてくる「可能性」はあります。
しかし、ここでも【超・重要】な注意点があります!
1歳の時点においても、ギフテッドかどうかを確実に判断することは、専門家でも非常に困難です。
この時期の発達スピードは、依然として個人差が非常に大きいものです。一時的に突出して見えても、それが将来のギフテッドネスにつながるとは限りません。これから挙げる特徴は、あくまで「後にギフテッドとされたお子さんによく見られたと言われる1歳代の特徴」であり、「可能性のヒント」程度に受け止め、決してチェックリストのように使わないでください。
言葉の発達が驚くほど早い
- 単語を覚えるスピードが非常に速く、1歳半を待たずに語彙が豊富。
- 早い段階(1歳前半など)から二語文(「わんわん、いた」)や三語文(「ママ、りんご、ちょうだい」)を話し始める。
- 大人が話している複雑な内容も、なんとなく理解しているように見える。
ずば抜けた記憶力
- 絵本を数回読んだだけで、内容やセリフをかなり正確に覚えている。
- 少し前に体験したことや、一度しか行っていない場所などをよく覚えている。
- 人の名前や物の名前をすぐに覚える。
数字や文字への強い関心
- 時計の数字、カレンダー、車のナンバープレートなどに強い興味を示す。
- 絵本を読むときも、文字の方をじっと見ている。
- 早い段階で数字やひらがな、アルファベットなどを自然に覚え始める。
高い問題解決能力の片鱗
- 欲しいものを取るために、椅子を持ってきたり、箱を積み上げたりするなど、自分で考えて工夫する。
- 型はめパズルや簡単なブロックなどを、教えなくてもすぐにマスターしてしまう。
- おもちゃの仕組みをすぐに理解し、大人も驚くような遊び方をする。
知的好奇心が旺盛で「なぜ?」が始まる
- 身の回りのあらゆる物事に対して、「これなあに?」と(言葉や指差しで)盛んに質問する。
- 納得できるまで知りたがり、探求心が非常に強い。
驚異的な集中力
- 興味を持ったこと(パズル、絵本、ブロック、砂遊びなど)に対して、周りの音や呼びかけも気にせず、非常に長い時間、一人で黙々と集中して取り組むことができる。
豊かな想像力と創造性
- 積み木や粘土などで、大人が思いつかないような独創的なものを作り出す。
- ごっこ遊びで、自分なりのユニークな設定やストーリーを展開させる。
強い感受性と共感力
- 人の表情や声のトーンから、感情を敏感に読み取る。
- 絵本や音楽に深く感動したり、登場人物に強く感情移入したりする。
- 「かわいそう」「〇〇ちゃんが泣いてる」など、他者の気持ちを理解するような言動が見られる。
これらの特徴が見られたとしても、それは単に発達が早いだけ、あるいは特定の分野への興味が強いだけ、という可能性も十分にあります。また、これらの特徴が全くなくても、ギフテッドである可能性もあります。一つの側面だけで判断せず、お子さんの全体像を見ることが大切です。
才能と表裏一体? ギフテッドが感じやすい「生きづらさ」とは
「ギフテッド」という言葉には、華やかなイメージがあるかもしれませんが、その突出した能力や独特な感性ゆえに、周りの世界との間に摩擦やズレが生じ、「生きづらさ」を感じてしまうことがあります。
例えば…
- 周りとのギャップ: 考え方や興味が同年代の子と合わず、話が通じなかったり、孤立してしまったり。
- 過敏さ: 音、光、人の感情などに非常に敏感で、刺激を受けすぎて疲れやすい。
- 完璧主義: 自分への要求水準が高すぎて、失敗を極端に恐れたり、常に満足できなかったり。
- 発達のアンバランス: 知的な発達は早くても、感情面や社会性の発達が追いつかず、アンバランスさに悩む。
- OE(過度激動): 様々な刺激に対する反応が、人一倍強く激しく現れることによる困難。
才能があるからといって、必ずしも楽に生きていけるわけではない、という側面も理解しておくことが大切です。
ギフテッドかどうかより、もっと大切なこと
「もしかして、うちの子はギフテッドかも?」 そう感じた時、親としてはその才能を証明したくなったり、特別な教育を受けさせたくなったりするかもしれません。
でも、少し立ち止まって考えてみてください。 子育てにおいて本当に大切なのは、「ギフテッドかどうか」というレッテルを貼ることでしょうか?
繰り返しになりますが、1歳という早期での判断は非常に難しく、不確実です。
「ギフテッド」という枠にはめようとすることで、その子のありのままの姿や、他の素晴らしい個性を見過ごしてしまうかもしれません。また、親の「ギフテッドであってほしい」という期待が、無意識のうちに子どもへのプレッシャーになってしまう可能性があります。
では、親として何を大切にすれば良いのでしょうか?
それは、目の前にいる我が子を、先入観を持たずに、愛情を持ってじっくりと見つめること。 そして、
- この子は何に目を輝かせ、夢中になっているだろう?
- どんなことに興味を持ち、何が得意なのかな?
- どんな時に心から楽しそうな笑顔を見せるだろう?
そういった、その子自身の「好き!」「楽しい!」「もっと知りたい!」という内側から湧き出るエネルギーを見つけ、それを大切に育み、その子のペースで伸び伸びと探求できるようサポートしていくことです。
好奇心の翼を広げる環境
子どもが興味を持ったことを否定せず、「面白いね!」「もっとやってみようか」と一緒に楽しみ、安心して試行錯誤できる環境を用意しましょう。
「できた!」より「やってるね!」を応援
結果を評価するのではなく、挑戦しようとする意欲や、夢中になっているプロセスそのものを認め、「見てるよ」「楽しそうだね」と温かく見守る声かけを心がけましょう。
無条件の愛情で土台を作る
何ができてもできなくても、「あなたはあなたのままで、ママとパパの大切な宝物だよ」というメッセージを伝え続け、揺るぎない自己肯定感を育むことが、すべての土台になります。
すべての1歳児は可能性の塊!個性を輝かせる子育てを
1歳児に見られるギフテッドの可能性について触れてきましたが、それはあくまで一つの視点であり、判断基準ではありません。
「ギフテッド」という言葉に一喜一憂するのではなく、目の前にいる我が子のユニークな個性を丸ごと愛し、その子らしいペースで歩んでいく成長の道のりを、一番の理解者として応援してあげることが、何よりも尊い関わり方ではないでしょうか。
すべての赤ちゃんは、計り知れない可能性を秘めた「ギフト」です。その子ならではの特別な輝きを信じて、大切に育んでいきたいですね。
もし、発達に関して気になることや、専門的なアドバイスが必要だと感じる場合は、決して一人で抱え込まず、かかりつけの小児科医や地域の保健センター、子育て支援センターなどに気軽に相談してみてください。きっと、あなたの気持ちに寄り添い、適切なサポートや情報を提供してくれるはずです。
そして、毎日たくさんの愛情を注いでいるパパさん、ママさん自身も、どうか無理せず、ご自身の心と体を大切にしながら、子育ての日々を楽しんでくださいね。応援しています!